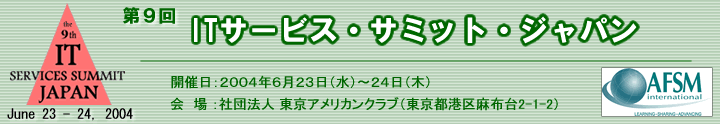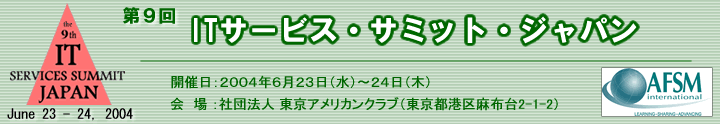| 6月24日 10:10〜11:00 |
EDSアジャイル・インフラストラクチャー
−ユーティリティー・コンピューティングと
インフラストラクチャーのアウトソーシング−
(EDS Agile Infrastructure
Utility Computing & the Outsourced Infrastructure) |
| 企業は今日、ユーティリティー・コンピューティングとは本当は何なのか、また、何ができるのかを懸命に理解しようとしている。 どうしたら、あなたの会社を、現状からこの新しい局面に持っていくことができるであろうか。 この講演では、企業を「アジャイル(敏捷な、機敏な)・エンタープライズ」へと変化させるための方策について論じる。 また、EDS社の最新ユーティリティーシステム、「アジャイル・インフラストラクチャー」プラットフォームについてご紹介するとともに、この新たな可能性がもたらす未来にも触れる。 さらに、敏捷性によって何層ものインフラストラクチャーをどう克服するのか、そして、EDS社が今日の顧客とのユーティリティーへの期待にどう応えているかについてもお伝えする。 |
EDSジャパンLLC
代表取締役副社長 兼 COO
ダグラス・ファウラー 氏 (Douglas M. Fowler) |
 |
1995年に入社後、様々なマネージメントの職を歴任し、現在は日本市場における企業のコア・ビジネス成長支援に取り組んでいる。
EDS以前は、リンク・コンピューター社(LINC Computer, Inc.)におけるアウトソーシング・チームのリーダーに3年間従事。 日本では、13年以上にわたり、この業界におけるマネージメント、セールス、マーケティング、ビジネス開発の分野での地位を認められている。
EDS入社後は、主要なアライアンス企業と金融サービスおよび小売業関連のグローバルな顧客を相手とする業務契約に寄与した。
2001年、EDS社とサン・マイクロシステムズ社の「サービス継続」契約締結に携わり、この契約によって、両社は、オンデマンドなITソリューションを相互提供する、15年に及ぶ戦略的アライアンスへと発展した。 |
| 6月24日 13:30〜14:20 |
ユーティリティー・コンピューティングのための
データーセンター管理標準仕様の構築 (DCML)
(DCML: Driving Utility Computing Standards) |
| クライアント・サーバーからインターネット・アーキテクチャーへという企業コンピューティング環境のドラマティックな移行は、サーバーおよびアプリケーションの大きな伸びに起因する。 多くの企業で、ITスタッフ戦力は数十のバラバラなシステムを管理しようとし、結果、複雑なデータ・センターを増やすに終わっている。 適切なロードマップなくしてこの混乱から抜け出すことは、困難だろう。 自動化されたオンデマンド・コンピューティングにおける最新のツール、データ・センター・マークアップ・ランゲージ(DCML)を投入しよう。 DCMLは、現在サーバーにある全てのものをデータ・センター全体に明確に示すための強力な設計図、データ・センターのコンテンツを管理する際の基本概念と標準仕様、および、データ・センターが構成されるべき手順をもたらす。 DCMLというデータ・センターの新標準がオンデマンド・インフラ構築の組織作りに果たす重要な役割について、ダレル・トーマス氏とスコット・クーパー氏による議論をお聞き戴きたい。 |
データセンター・マークアップランゲージ(DCML)協会
スコット・クーパー 氏 (Scott Kupor) |
 |
| オプスウェア社の国際マーケット開発、および、戦略的パートナーシップの交渉を含めたオペレーションを担当する。 日本で、数百万ドルにおよぶオプスウェア社初の国際パートナーシップを立ち上げ、同社最大のビジネス向けエンド・ユーザー・ソフトウェア・ライセンスの商談をまとめた。 以前には、オプスウェア社の財務計画および事業開発担当副社長に従事し、ラウドクラウド社(オプスウェア社の旧名)マネージド・サービス部門のEDSへの売却、そして、オプスウェア社を独立したソフトウェア企業として再構築する際に、重要な役割を果たした。 |
| 6月24日 11:00〜11:50 |
ITオートメーション
- ユーティリティー・コンピューティングの基盤 -
(IT Automation - The Foundation of Utility Computing -) |
オンデマンド、従量課金、アダプティブ・インフラなど、顧客がどう呼ぶかにかかわらず、ユーティリティー・コンピューティングは、現実のものとなっている。 CTOは、品質を犠牲にすることなく、どのようにしてITインフラを最適化するかの使命をおびている。 品質を犠牲することなく、いかにITインフラを最適化すべきか?ユーティリティー・コンピューティングは我が社に適したものだろうか? この講演では、これらの問題に取組み、データセンターにおいて自動化が果たす重要な役割と、データセンターの自動化(DCA)がユーティリティー向上のどの局面においても重要である理由について議論する。
事例研究を用いて、このプレゼンテーションでは、データセンターの自動化によるユーティリティー・コンピューティングが、IT部門にいかにメリットをもたらしたかをお見せする。 事例によっては、以下についてさらに詳しく述べている。
・ オートメーションのもたらすROI
・ 準備からフル・サーバー・ライフサイクル管理まで
・ 資産管理の最適化戦略
・ データセンター・インテリジェンスの実現 |
オプスウェア社
副社長兼本部長
スコット・クーパー 氏 (Scott Kupor) |
 |
| オプスウェア社の国際マーケット開発、および、戦略的パートナーシップの交渉を含めたオペレーションを担当する。 日本で、数百万ドルにおよぶオプスウェア社初の国際パートナーシップを立ち上げ、同社最大のビジネス向けエンド・ユーザー・ソフトウェア・ライセンスの商談をまとめた。 以前には、オプスウェア社の財務計画および事業開発担当副社長に従事し、ラウドクラウド社(オプスウェア社の旧名)マネージド・サービス部門のEDSへの売却、そして、オプスウェア社を独立したソフトウェア企業として再構築する際に、重要な役割を果たした。 |
| 6月24日 12:40〜13:30 |
コスト・センターからバリューセンターへ
- ユーティリティー・コンピューティングへの移行方法 -
(Utility Computing - From Cost Center to Value Center) |
ユーティリティー・コンピューティングは、魅力的な概念である。 コストを削減し、サービス品質を向上し、そして、企業の事業目標にIT組織を適合させる。 しかし、今日、どのようにしてそれを実現できるのか?
ベリタスは、既存のデータセンターに対して、今すぐユーティリティー・コンピューティングに向けて着手できるソリューションを用意している。 それは、システム的なビルディング・ブロック方式であり、それぞれの段階において、明らかなメリットを創出する。 |
ベリタス・ソフトウェア株式会社
取締役 マーケティング担当
ジェローム・ノール 氏 (Jerome Noll) |
 |
ベリタス・ソフトウェア社のマーケティング担当役員として、日本における全社のマーケティング活動を統轄する。 特に、戦略的顧客関係およびブランディング活動に積極的に取り組む一方、自社のグローバル・セールスや収益のターゲットに応え、非常に大きく貢献している。
1999年の入社以前には、シンガポールに拠点を置くAuspexSystems社のセールス・マーケティング部門で南アジアを担当した。 またその前には、同社のシリコン・バレー本社において、グローバル・フィールド・マーケティング・チームを率いた。
長い専門的キャリアにおいて、サン・マイクロシステムズ社およびNCR社では、さまざまな部門の責任者も担当している。
ジョージタウン大学卒、マーケティングおよびコンピューター・サイエンス専攻。 |